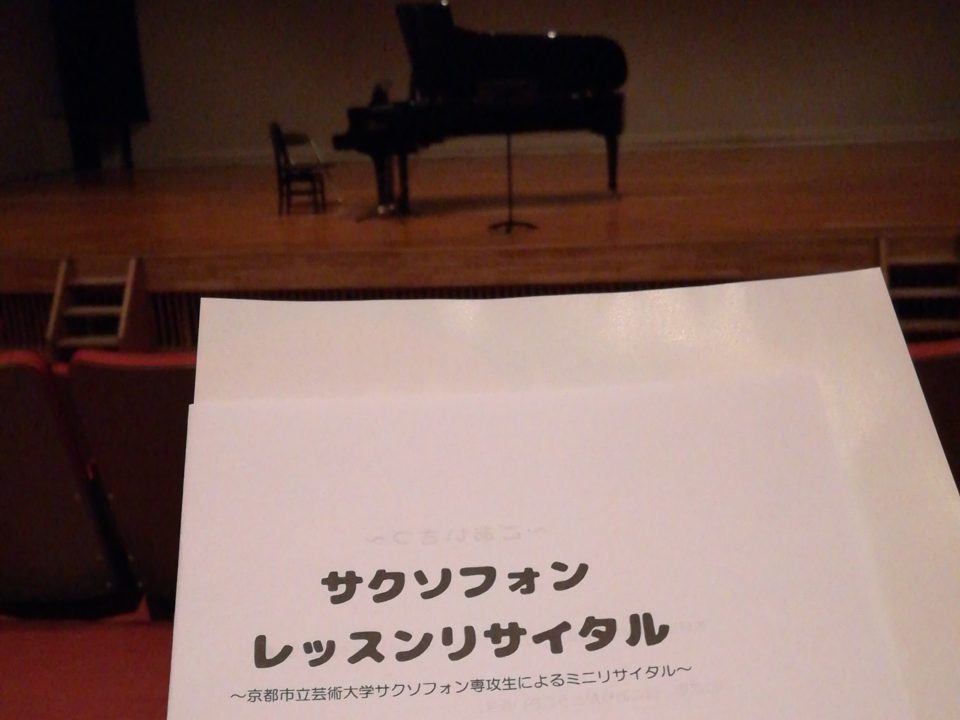先日、京都芸大サックス専攻のレッスンリサイタルで、ゲストティーチャーとして講評させていただく(センセイと呼ばれる仕事に就いたことがないこの僕が!)という、貴重な体験をさせていただきました。レッスンリサイタルはサックス専攻が独自に行っているもので、1人30分という枠で各自でプログラムを組み、演奏のクオリティだけではなく、ステージマナーやトークの内容、しゃべり方なども含めて、コンサート全体としての魅せ方・伝え方を学ぶというものです。
僕は学生の演奏をあれこれ言える立場ではないので、何かみんなの役に立つようなことが言えるだろうかとドキドキしながら聴いてたけど、始まってみると「もし僕がコーディネートするならこうしてもらうかな」というところがいくつか見つかりました。例えばクラシックに馴染みがない人たちを想定してしゃべってるつもりでも、もっと伝えないといけないところをはしょっていたりとか。例えばこれがフランスの有名なサクソフォン奏者のリサイタルだったら、こんな立ち居振る舞いはしないだろうなと思う部分があったりとか。
僕は普段、イベントやパーティーの現場で、クラシックに馴染みがない担当者とお話をして、正直なご意見をたくさんいただいています。また、生のコンサートを聴く機会がほとんどない田舎で過ごしていた僕は、クラシックと無関係に暮らしている人が持っている音楽家のイメージは、テレビで見る超一流の演奏家の姿が基準になっている、ということを知っています。リサイタルを聴かせてもらいながら、もしかしたら僕は、クラシックを専門にやっている人たちよりも、少しだけクラシックビギナーの気持ちをわかっているかもしれない、それが僕の強みなのかも、と思っていました。
自分の短所ってすぐにたくさん言えるけど、長所って案外わからないものです。京芸ではキャリアと名がつくところで働かせてもらっていますが、自分自身の最大のウリは何なのか、実はよくわかっていません。今回こうして、誰かを客観的に判断しようとしたことで、それが跳ね返って自分を客観的に見る機会にもなったようです。誘ってくれたサックス専攻の皆さん、國末先生、ありがとうございました!
ちなみに。実は僕がゲストティーチャーだということをちゃんと認識してなくて、単なる聴衆のつもりで割と気軽に行ったので、コンサートの最後にステージで講評していただけませんか?と言われてドッキリかと思いました笑